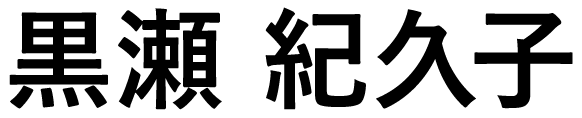風薫る五月がやって来る。 五月になると、この言葉通り風が薫る。 至る所で花が開き、芽吹く新芽もその生命の力とともに微かな香りを漂わせる。
心地良い香りは私たちの感性を和ませてくれる。 花の香りも食べ物の香りも、それはあらゆるバリアを越えて細胞の隅々にまで届けられる。
そんな香りを感じながら生きていると、いつしか我々は香りというものに対しての感覚が研ぎ澄まされ、時には偽の香を見破ることができるようになる。 例えば人工のフレーバーが施されている飲み物や、ジャムなどだ。 芳香剤にも人工的な香りが付けられているものがある。 何故か、そういった偽の香は心地よさが長持ちしない。 いつか飽きてしまう。 それに比べると、毎年決まって薫る五月の風は何年経っても懐かしく心地よくて、いつしか心が素直になる。 全ての人が受けることの出来る大自然の恵みだ。
それを受けて、今まで多くの天才たちが曲を創り、絵を描いた。 その作品からは豊満な香りが立ち昇る。
演奏にも香りというものがある。
音楽には演奏によって表されるものが、音以外にもたくさんある。 推進力とも言われるエネルギーや、湧き上がる力は、その中でも最も感じられるものだろう。 いつしか導かれているような道を想わせる流れもある。 励まされ、鼓舞されているような動きもある。 いつまでも寄りかかっていたいような優しさもある。
その中で香りというものは、最も崇高なものだと私は思っている。 それは絶えず感じられるものではなく、その存在はとても曖昧だ。 しかし、それはちょっとした流れの端に隠れていたりする。 音の連なりの中に潜んでいたりする。 ふと、一陣の微かな風が花の香りを運んできて、次の瞬間にはそれをまた私達の元から運び去るように、音楽の香りも空中を漂っては見え隠れする。
その香りからは、思わぬものが一瞬透けて見える。 人がその言動とは別に、本人の自覚しないところでその本性や生い立ちが滲み出るように、演奏から醸し出される香りも、当時の街に漂っていたであろう空気、作曲家のノーブルな感性の息吹などを感じさせる。 それは作品の持つDNAのようなものだ。 その香りが感じられると、それまでの歴史や当時の文化を背負って生まれたその作品の声を生で聞いたような感動に、鳥肌が立つほど心が震える。
この演奏から醸し出される香りというものは、しかし、全ての演奏家が受けることの出来る恵みではない。 立派な非の打ちどころの無い演奏でも、香りのない演奏はいくらもある。 また、香りを求めない聴き手も多い。
この説明できないもの、技術や音楽性までもを超えた実態のないものが感じられる演奏は、その演奏家の才能の成せる技なのだろう。 それは、教えられるものでもなく、求めて手に入るものでもないからだ。
崇高な香りを放つのは聳え立つ山の頂に咲く、手の届かない一輪の花なのかもしれない。