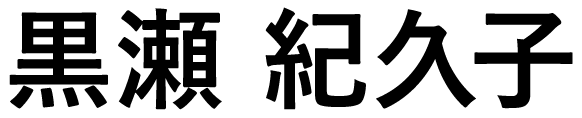私がまだ高校生の頃、所属していたクラブでカミユ研究をしたことがある。 文化祭での発表だった。
大した知識もなく、理解力もまだ乏しい10代の頃だ。 それでも、「実存主義」という言葉は私にとってまぶしくて、未知の世界であったにもかかわらず、 大変魅力的に感じられた。 分からないなりにカミユの小説をたくさん読んだ。 その中に「シジフォスの神話」というものがあった。
その小説がどんな内容だったのか、どんな意図を持っていたのかということより、私はシジフォスの神話そのものに驚き、心を惹かれた。 知らなかった世界がそこにあった。
今思えば、そのシジフォスの神話との出会いは、ぼんやりとした 意識の下で、未知の世界の果てしない広がりを 私に感じさせていたように思う。
それはまだ10代の高校生が自我に目覚めて生きた、ほんの数年体験した世界とは比べ物にならない広さだった。 その得体の知れない世界は私にとって混沌とした不安や恐れの 入り混じったような ものだった。 はっきりと意識すらできない心の奥底にそれはあった。 そしてそれは、私の脳内の新たな領域に 未知の世界から感じることや、得た知識を刻みつけるのだという予感を感じさせた。
そんな心を抱えながら、私は訳のわからない予感や不安と共に10代を過ごした。
「シジフォスの神話」はそれ以来ずっと私の中に留まり続け、時折その存在を大きく主張した。 何度も私は文中にそれを引用した。 そこに私のピアノ人生を重ねることもしばしばだった。
当時の霧に包まれたような意識は、約半世紀を過ぎた現在、ようやくこうして言葉にすることができるものだった。
やがて年数が経つにつれ、私の中の空白の領域に知識や感覚を入れていく事は、次第に心地良いものになった。 蓄積されていく体験や、人とのつながりに支えられてそこに快感さえ覚えるようになった。
歳を重ねるにつれ、当時意識を包んでいた霧もモヤが晴れるように消えていった。 そこに生きる指標のようなものが はっきりと置かれたからかもしれない。 そして私は空白の領域をはっきりと自覚するようになった。
その空白の領域の広さは昔のままだ。 つまり果てしなく広い。
10代の頃と違っているのは、そこに不安や恐れがあるのではなく、好奇心にも似た期待や憧れがあることだ。
それが今まで生きてきたことの果実なのかもしれない。 そんなことを考えながら今日もシジフォスのように音に向かう。 私の空白の領域に新たに何かを刻み付けることができる事を期待しながら。