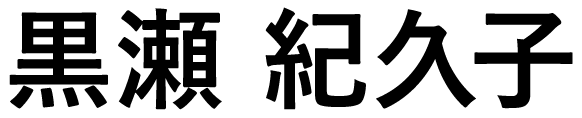人は様々な顔を持っている。
その日、その時間の気分や身体の調子や、環境によってその顔はどんどん変わる。
悪い具合に、調子の良くない人に出会えば、その人は良い顔をこちらに向けない。 同じ人でも、気分の高揚している時に出会えば、生気に満ちた良い顔を見せてくれる。 その顔の差は正直な人ほど大きい。
応対する相手によって目まぐるしく顔が変わる人もいる。 その変わりかたが意図的な人もいれば、自然とそうなっている人もいる。 いずれにしても、正直な人は「思いが顔に出る」というように、その裏にある心が透けて見える。
思いや、調子の波や、環境の良し悪しを完璧に隠す人もいる。 そんな人の顔からは逆の思いが想像されたり、カムフラージュの巧みさ故に、いつ会っても同じ顔にしか出会わないこともある。
人は誰でも百面相を持つ。 そんな人の顔ほど興味深いものはない。 それこそ、生きている証のようなものだ。
その顔の変化が芸術にまで高まることがある。
まず、演劇やバレーなどの舞台芸術だ。 言葉よりも顔がモノをいうことも多い。 そこには、その役になりきって、その人物に同化してしまっている役者やダンサーがいる。 そして考えられないほどの規模のオーラが満ち溢れる。 オペラ歌手は声だけでなく、顔の表情の訓練も厳しい。
ある写真家が、演奏中の音楽家の顔を撮るほど面白いものはないと、ある時私に言った。 刻々と変わるその表情はその音楽の中に書きこまれたストーリーや風景そのものだ。 音楽家は曲が始まるや、終わりに至る長い道のりの旅に出る。 その一部始終が音と共に顔にも現れる。 それを見られたくないと、長い黒髪で顔のほとんどを覆って演奏したピアニストもいた。
私はといえば、すぐに思いが顔に出るので、日頃から修養が足らないと自戒している。
しかし、演奏に関しては、顔のことなど気にせずに、全ての壁を取り払って自らを音楽に合体させたいと思っている。
今日は果たしてどんな風に音楽と一体となれただろうか、演奏中の顔は音の表現を反映していただろうか。 それだけ多彩な表現ができただろうか。 雑念の影が顔をよぎったのではなかったか。 演奏後、いつもこんなことを自問する。
演奏においては、百面相も二百面相も持ちたいものだ。