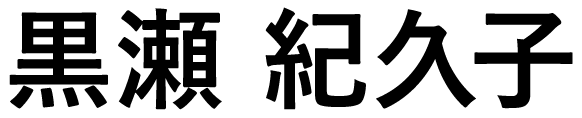先日、久しぶりに 「赤とんぼ」 を聴いた。 私の企画した小さなサロンコンサートでのことだ。 アンコールに歌われた 「赤とんぼ」 は誰もが知る山田耕筰の歌曲だ。 クラシックの演奏会の中で、この曲がアンコールに取り上げられる事は群を抜いて多い。 私も、何度も声楽の演奏会の最後にこれを聴いた。 しかし、そのどれもが聴衆参加型、つまり 「皆さん一緒に歌いましょう」 というものだった。 それまで無言で音楽を聴いていた聴衆がこの懐かしい歌を楽しそうに歌う。 そして和やかな雰囲気の中、演奏会がお開きとなる。 「赤とんぼ」 はいつもそんなふうに扱われていた。
冒頭、 「久しぶりに」 と書いたのは、今回の 「赤とんぼ」 が聴衆が参加することなく、バリトン歌手によって 1つの日本歌曲として格調高く歌われたからだ。 長年 「赤とんぼ」 は聴衆とともに歌われていて、1つの歌曲として聴いた記憶はないくらいだった。
そして、最終節がピアニッシモで歌われ、この曲が締め括られようとした時、不覚にも目に涙が溢れてしまった。 この演奏会を企画した者として、実は主催者にも、聴衆にも涙を見せたくなかったのだが、その時の私は1人の聴衆になりきっていたのだった。
後日、私は自らの体験をもとに、このときの涙の分析を試みた。
何故、あの時涙があふれたのだろう?
聞こえてくる旋律が、歌詞が、聴く人のそれまでの体験や愛しい思い出と重なって 涙を誘う事はよくあることだ。 しかし、私の中にはあの時、何の思い出も蘇って来なかったし、私の心は感傷的にもなっていなかった。 では、何が私を涙させたのだろう。
それはあの曲自体の持つ力、美しさだったのだろうか。 声自体の美しさだったのだろうか。
演奏されたものが、聴く者の琴線に触れる時、その場には不思議な世界が拡がっている。 その世界では無数の糸が縦横に乱れ伸びている。 あるものは音に連なり、あるものは響きとともに光り、あるものは情景をも描きだす。 言葉に繋がっているもの、詩の醸し出す色に連なるものなど、 無数の糸は絡み合いながら聴く者の心を覆う。 そのうちの何本かの糸が心の奥にまで刺さる時、人は 感涙に咽ぶ。 理由などない。 説明ができないほどのたくさんの糸が呼ぶ感動が、心を満たしているのだ。
私にとって、 「赤とんぼ」 でこのような涙に到達するには、この曲と真摯に向き合い、芸術の尊厳とともに歌い上げる鍛え抜かれた歌唱が必要だった。
「よく知っている曲」 がそう簡単には覗けない美しい世界に連れて行ってくれる。 そんな演奏会も魅力的だ。